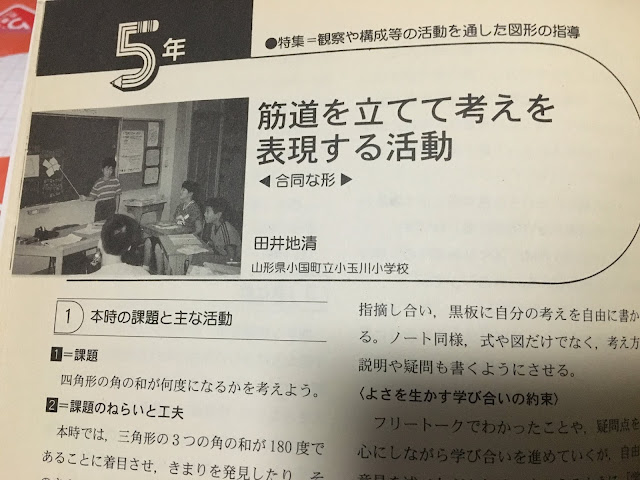今の教育界では、「主体的・対話的な学び」を求めています。山形県でも、「探究型の学習」を提唱しています。目指すところは同じです。
この主体的・対話的な学びというのは、どういう学習を定義しているのかは、たくさんの書籍を読めばわかると思います。
横浜国立大学の石田淳一教授は、主体的・対話的な学びを育てる授業づくりのコツを提案しています。
⑴学び合いの教室空間
教室をコの字にしたり、最初からグループにしたり、学び合うための空間が必要です。全体の学び合いでは、机を後ろに移動して全員を黒板前に座らせる方法も有効です。
⑵能動的問題把握を促す問題提示の工夫
問題定時にはいろいろな方法があります。図や表だけを提示して気付きを話し合ったり、どんな解法があるかを話し合ったりします。従来の授業では、問題提示→見通し→自力解決という流れがありましたが、問題の段階ですでに学び合いが始まります。最初から解法の話し合いになることもあります。大事なことは、子どもたち自ら色々な気づきをさせるということと、相談などのプチ話し合いを認めていくということです。そして、みんなで見通しを共有することですね。
⑶グループ学習の取り入れ方の工夫
見通しをもったら自力解決という課題解決型からの脱脚です。問題の意味も理解できない、見通しももてないという状態で一人で問題を解決できるはずはありません。自力解決できる子どもは、私の経験上数パーセントくらいでしょうか。
グループの組み方も最初は意図的なメンバーがいいと思います。でも、最終的にはどういうメンバーでもやっていけるようにするのが理想です。
グループで話し合う前に、プチ自力を入れる場合があります。そういう場合は、グループでの話し合いが活発になります。見通しを全体ではなく、グループで行う場合もあります。ある程度、学び合いに慣れて力がついた時に有効です。
⑷間をとって、相談・算数トークが自然にできる指導
いろいろな場面で、相談タイムを設定します。「相談させてください」と、子どもたちから自発的に要求してくるようになります。また、算数 トークは、今後とくに重要視される学び合いの中心となるものです。算数トークの善し悪しでよい学び合いの授業になるかどうかが決まります。
⑸子どもが授業を進める学び合いの指導
主体的に学ぶということですが、算数トークができるようになると、子供たち自から考えをつなぎ合うことができるようになります。ちなみに、うちの学校では、「言葉のキャッチボール」というものがあります。
⑹聴き方・話し方指導
学び合いでは、言うまでもありませんね。
⑺一人一人が目的をもって話し合いができる指導
何を明らかにしようとした話し合いかを考えさせます。ふつうは、「はかせどん」です。
⑻つなぐを促す教師の働きかけ
いきなり意見をつなげるようになるわけはありません。「今の考えどう?」「その考えってどういうこと?」などと常に全体に問いかけます。「考えをつなぐ」ことをうながすことですね。
⑼子どもがまとめをつくる指導
本時のまとめをグループで考えさせました。ここでも学び合いです。
⑽学びの実感ができる振り返りの指導
私は、「わかったこと」「いいなと思った考え」「もっとやってみたいこと」という点について振り返りをさせています。石田先生からのご指導で、ノートを交換して互いに読み合い、いいなと思った部分に線を引かせるということもやってみました。振り返りでもやっぱり学び合いです。